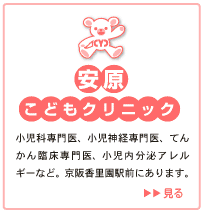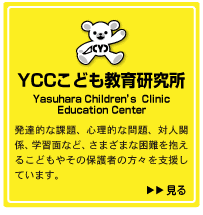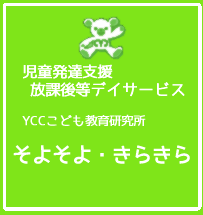2024年度事例検討会:宮本ゆみこ のびのびキッズ代表
●2025年3月14日事例検討会
実施なし
●2025年1月9日事例検討会感想
割愛させていただきます。
●2024年11月14日事例検討会報告
割愛させていただきます。
●2024年9月12日事例検討会報告
今回の主訴は
①施設入所して順調に暮らしている中学生男子への施設入所が必要な理由の説明
②施設から高校に通うがその進路選択
③兄弟への心のケア
です。
今回は安原ドクターと伊丹先生のお二人のコメントが聞けました。
①について
施設側から、家族が傷ついて来たことを、両親から本人に話してほしいと言われたそうです。
両親との面談時に帰りたいとは言わないそうですが、施設で頑張っているのでいつ帰れるのかと、施設の方に聞くそうです。おそらく施設側としては、なぜ施設入所に至ったかの認識が本人の中に足りないと思われ、人の痛みを知って、高校3年までの施設生活で他者感情の理解を促せたいと思われての要望かもしれません。
しかし、両親にとっては不安です。下手な説明をして自暴自棄になりはしないか、せっかく順調に暮らしている今がそのタイミングなんだろうか、もっと違う説明はないだろうか、と悩まれているようです。
コメント→家族が傷ついたなどと、嫌な記憶を引き出すような事は言う必要がない。大事なのは彼が幸せな未来を送れるための提案をすること、
施設と家庭では、ルールが違う。家庭に戻っても落ち着いて暮らせるようにするにはルールを徹底する必要があるが、簡単ではない。施設でも投薬は続けたほうが良い。
攻撃性が強い場合、脳や神経伝達物質の不具合が影響していることが多いので、攻撃性を抑える投薬を検討させるべき。
また自己理解を深め、投薬の必要性を説得するのは医師の役割。
②について
自閉症の特性には、集団生活の刺激が多すぎ、大きなトラブルを誘発することが多い。彼の場合も、毎日通学は負荷が多すぎる。
おすすめは、通学が少ない通信高校や高校の資格が取れる柔軟で居心地が良いフリースクール
③について
兄弟は、きっと今まで自分たちが二番目の扱いだと思ってきたはず。
一人一人との時間を作り、じっくり話を聞いてあげることが大事。
初めは暴れてきた次男の悪口や両親への文句を言うかもしれない。
溜まった毒は吐き出させるためにも傾聴に徹し、共感や気持ちの代弁
に心がけてほしい。
両親は自分たちの事にも気をかけていると納得すれば
やがて次男の苦しさにも気がつくはず。待とう。
もっと深い話が交わされましたが、プライバシーに関わるのでこれくらいにしておきます。今回も両大先生の、臨床経験からの的確なコメントに、学びが多い検討会となりました。
●2024年7月11日の事例検討会報告
ギフテッドに近い認知能力がある小4と多動が強くて学校での学びが
思うようにいかない小2の兄弟男子の事例で、ふたりとも幼児期に診断名は
ASD
保護者の主訴は登校渋りが強い2人への関わり方でした。
ふたりとも言語能力が強くて思考力も充分にありながら
その力は学習の成果に現れにくい検査結果プロフィール
このような場合は、得意な認知の活用が普通で
学校の支援級でも塾でも、弱さを得意で鍛えること結構実践されていました。
兄は大人並みの読みスキルは非常に高いのに、漢字は二年遅れの習熟
弟は言語能力はそこそこ高いものの、形の把握は非常に低くワーキングメモリーも弱いので、読み書き計算が弱い限局性学習症は明らか
親御さんの聞き取りから違和感を覚えたのは
学校も塾も、この子たちの自立活動をちゃんと検討してくれているのかな、という疑問でした。
確かに、苦手な書字活動に得意な力をまあまあ使ってくれているのですが
本当にこの子達に必要な自立活動だろうか、
せっかくの言語力の強みを更に深めて自信に繋げることはあるんじゃないか?
と思えた事例です。
そこで伊丹先生にその疑問をぶつけてみました。
先生の答えは
「不安の軽減に心理的支援と対人関係支援が親御さんの主訴にあっています。
この子達はこの学校だから登校しているのです」でした。
はっとしました。
どちらかというと、学習指導のレベルアップを描いていたので
心理面と対人面への支援、という方向に目を向けていなかったなあと思いました。
改めて自立活動の内容を学ぶ必要を感じた事例でした。
またドクターからは、いつものように思いっきりのよい常識への疑問や提言や
お薬のお話しや診断名への疑問など出されて
お医者様との出会いも大事なことを感じました。
●2024年5月9日事例検討会報告
今回は、小学校5,6年は不登校でしたが、中学からは連休明けも登校できた事例です。
主訴は、せっかく自発的に登校しはじめたので、また不登校にならないように環境をどのように整えていけばよいか、
Wisc5とVailand2の結果も踏まえて
学校と家庭でできる配慮や支援を検討してゆきました。
背景情報を読むと、本人が徐々に登校への意欲を上げて行く様子がとてもよく伝わってきました。
感覚も思考もとても繊細なお子さんですが、言ってる言葉とは裏腹に,
何とか不登校から脱しようとしていることがとても伝わってきました。
彼が中学から登校できた要因には次の事が考えられました。
①オンラインスクールで友人ができた事で、自分と同じような状況にいる子がいて、学校に行きたくても行けない子がいるとわかってちょっと気が楽になった事
②オンラインスクールで友人ができたことで、イベント参加して達成感を得た事でオンラインスクールに参加する日程を増やす事ができた
③一年前の事例で,イベントに参加できる事をターゲットにしようというアドバイスを受けて、学校と家庭が共通理解をして、それにそって学校の先生が程よい距離感を保ってこどもと関わり続ける
何とマラソン大会にも参加できていました!
④中学は小中一貫校で、校長は一緒、職員室も一緒で、常に配慮が必要な子の支援情報の情報共有がしやすい事
⑤大きな環境変化はない事
⑥保護者が抱える焦燥感や不安が、昨年の検討会である程度落ち着く事ができて、見守る姿勢が安定してきた事
などが考えられました。
検査結果から言える配慮は
①知識の蓄えも語彙の知識も年齢相当だけど、状況に応じて言葉を運用する弱さがあるので、表面的に捉えがちで、抽象的で曖昧な言い方はせず、具体的な言い回しを心がける。
例 大声で怒鳴るように母に暴言のように当たってきたら
「優しく言って」×→「静かに言って」
②絵があると理解が進むので、言葉と図や状況と結びつける支援をする。
図の提示とともに,言葉で説明する。
それと、「自発的な行動を褒めすぎない」というのも彼への大事な支援です。
やりたくない事があると
「学校行ってるから●●せんでいいやろ」という事があるそうです。
不登校から登校すると、学校に行くだけで十分だと親御さんも先生も思うかもしれないし、
やっぱりいっぱい褒めたくなります。
でも、彼は自分から登校しだしたので、内的動機付けからの行動な訳です。
それを褒めすぎると、さきほどのセリフになるので、
褒めすぎないという事がコツになるようです。
また学校でも、定期試験がありますから、どういう風に言葉掛けしたらよいか迷われているようでした。
「定期試験を受けるのは当たり前で,勉強しないといけない」
と、当然のように伝えてくださいと
伊丹先生のアドバイスが飛びます。
運動部にも所属して頑張っているし友人関係もとてもよいようです。
でも、家では篭りきりで,ゲームをしているようです。
今は学校に適応しようとすごく頑張っているので
家ではダラリとしてバランスを保っているのかもしれないですね。
しかし、今後も登校し続けられるには、遅れている学習への手立てをしないといけません。
そのためには自己理解を促し、学習への意欲を喚起する必要があります。
学校では、彼の得意そうな教科や内容を観察してアドバイスしてくださったり
部活がない試験前に、声かけして放課後の学習室での学習を促してくださると言ってくださいました。
働き方改革のせいで、
今回も学校の担任の先生たちは参加いただけなかったですが
教頭先生が代表で出てくださり、
今回の検討会の報告をして下さると約束してくださいました。
素晴らしい教頭先生でした。
「この学校だから登校している」と伊丹先生
頑張れと願わずにはいられません。